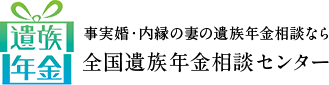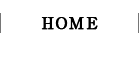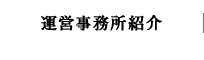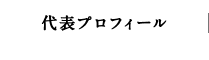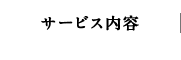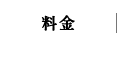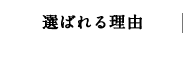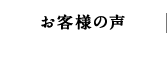カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (2)
- 2023年9月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2015年8月 (14)
最近のエントリー
HOME > 事例集 > 社会保険審査会事例 > 医療機関同意書に「知人」と書かれても内縁の妻と認められた事例
事例集
医療機関同意書に「知人」と書かれても内縁の妻と認められた事例
公開日: 2025年4月 9日 更新日:2025年4月10日
【社会保険審査会裁決事例】※当センターがサポートした案件ではありません。
平成30年(厚)第257号、平成30年(厚)第557号、令和元年5月31日裁決
主文 原処分をいずれも取り消す。

事案概要
請求人は、厚生年金保険法の規定による特別支給の老齢厚生年金の受給権者であったAが死亡したので、その内縁の妻であるとして、遺族厚生年金及び未支給年金の請求をしたところ、請求人に対し「生計を維持されていたとは判断できないため。」という理由により、不支給処分とした。請求人は、原処分を不服として、審査請求を経て、社会保険審査会に対し、再審査請求をした。
争点
本件における具体的事実関係に照らして、Aの死亡当時において、請求人がAと生計を同じくしていた事実上婚姻関係と同様の事情にある者であったと認めることができないかどうか。
結論
Aの死亡当時において、請求人は、Aと生計を同じくし、かつ、Aによって生計を維持した事実上婚姻関係と同様の事情にある者であったと認められるのであるから、請求人には、Aに係る遺族厚生年金及び本件未支給保険給付が支給されるべきであり、これと異なる趣旨の原処分は、いずれも妥当でないから、取り消されなければならない。
以上の理由によって、主文のとおり裁決する。
判断理由
前記1で認定した事実及び本件記録によれば、Aの死亡当時において、請求人がAと生計を同じくしていた事実上婚姻関係と同様の事情にある者であったと認めるのが相当である。
すなわち、前記1⑻エ及びオによれば、会員証等に記載の雅号の変遷及び会員証等と一体となった郵便はがき部分に記載された宛名住所から、雅号を「I」又は「I’」として、f会員証を取得した後、g会員証を取得していた者は請求人であると推認でき、
また、本件申立書及び前記1⑼によれば、請求人は、平成○年○月に勤務先を退職後、同年○月から、c宅においてAと同居し、Aと夫婦としての生活を始めた旨を陳述しているところ、同月前の平成○年度においては、請求人は雅号を「I」とし、そのf会員証はb宅に送付されていたことが認められ、平成○年度及び平成○年度ないし平成○年度においては、請求人は雅号を「I’」に変更し、会員証等と一体となった郵便はがき部分が確認できる平成○年度のf会員証及び平成 ○年度のg会員証はc宅に送付されていたことが認められ、「I」から「I’」への雅号の変更及び会員証等の送付先住所の変更は請求人の上記陳述とも符合することが認められる。
そして、平成○年○月○日の本件宅急便控も依頼主である請求人の住所はc宅であることが認められ、本件実施報告書によれば、平成○年○月○日に、住所をc宅とする請求人がd社に対し電子楽器の修理サービスを依頼し、平成○年○月○日に同サービスが実施されたが修理完了できなかったことが認められ、本件納品請求書によれば、請求人が「G’」として、同年○月○日に修理できなかった電子楽器に係る部品をd社に発注し、同年○月にはc宅において部品交換による修理がされたことがうかがえるのである。
さらに、上記1⑻クによれば、平成○年の年賀状は宛名を「G」としているものの、宛名住所は「○○○○○○○○○ A様方」とされ、それ以外の平成○年、平成○年、平成○年及び平成○年のものは、いずれも、宛名住所はc宅とされ、宛名には請求人が「G’」(Aとの連名を含む。)と記載され、そのうち平成○年のもの以外は、Aとの連名であることが認められるのである。
加えて、前記1⑻キによれば、Aが平成○年○月○日ないし同年○月○日付けで作成した本件医療機関同意書の「家族または保証人」欄には、いずれも、その続柄を「知人」とはしているが請求人の署名押印が認められるのである。
そして、本件記録中、請求人の主張は首尾一貫し、不自然な点も見受けられず、これらを考え併せれば、前記1⑷からは、請求人とAが住民票上同一住所に住所を定めていたことは認められないものの、請求人は、少なくとも、平成○年の正月には、c宅で起居するに至り、Aの死亡当時までの間、c宅においてAと同居していたものと認めるのが相当であり、請求人が「G’」や雅号「I’」を名乗り、本件医療機関同意書の「家族または保証人」欄にも署名押印していたことを考え併せれば、請求人とAは、その間、前記⑴ア及びイの2つの要件を備えていたと認めるのが相当であり、事実上婚姻関係と同様の事情にある者であったと認めるべきである。
生計同一関係についても、上記説示のとおり、請求人とAは、少なくとも、平成○年正月頃からAの死亡当時までの間、c宅において同居していたことが認められるところ、前記1⑻イ及びウからは、請求人がd社に依頼した部品代及びその取付料がA名義で支払われていることも認めることができるのであるから、請求人とAは、前記⑴ウに該当すると認めるのが相当であり、Aの死亡当時において、生計同一関係にあったと認めるべきである。そして、請求人が基準額以上の収入又は所得を将来にわたって有すると認められる者以外のものであったことについては明らかなのであるから、請求人は、Aの死亡当時において、Aと生計を同じくし、かつ、Aによって生計を維持した事実上婚姻関係と同様の事情にある者であったと認めるべきである。
なお、本件医療機関同意書に記載された請求人の続柄が「知人」であることやAの葬儀に係る喪主が請求人ではなく長男Dであったことについては、前記1⑼によりうかがえる事情からも不自然な点はなく、上記判断を左右するものにはなり得ない。
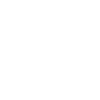 本案件のポイント
本案件のポイント
本裁決例は事実婚関係で「同居、住民票の住所が別」という案件となります。認定基準によれば、生計同一関係の取扱に関しては、下記の通り
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっている
が、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること
このうち、同居で、住民票上の住所が別の案件に関しては、上記ウの(ア)に該当することを証明する必要があります。
本裁決例は、裁決書をみるかぎり認定基準別表6に例示されている証明資料として、連名の郵便物の提出がうかがえますが、連名の年賀状の評価は年金事務所段階では非常に微妙(消印がないため)であり、各年金事務所により有効・無効と考え方が異なるケースがあります。
おそらく、本件では年金事務所での審査・決定において、連名の郵便物が評価されず、別表6の資料の提出がないという判断で不支給決定されたものと思われます。
一方、再審査請求では、過去の社会保険審査会の裁決例をみるに、連名の年賀状でも「連名の郵便物」として評価された事例がありますので、本件においては、有効な資料として評価されたと考えられます。
また、会員証、宅急便控、電子楽器の修理サービスの実施報告書や、納品請求書や同居していた住居宛の郵便物から、両者が同居していた事実が確認できることや、
医療機関同意書の続柄に「知人」として記載されていたことに関しては、一見マイナス評価にも見られかねないと思われますが、「家族または保証人」欄にも請求人が署名押印していた事実について鑑みれば、知人と書かざるを得ない状況であった為、続柄に知人として記入しただけで、実態としては内縁関係であったと社会保険審査会において評価されたと考えられます。
以上のことから、請求人はAによって生計を維持した事実上婚姻関係と同様の事情にある者という結論になりました。
おそらく、本件では年金事務所での審査・決定において、連名の郵便物が評価されず、別表6の資料の提出がないという判断で不支給決定されたものと思われます。
一方、再審査請求では、過去の社会保険審査会の裁決例をみるに、連名の年賀状でも「連名の郵便物」として評価された事例がありますので、本件においては、有効な資料として評価されたと考えられます。
また、会員証、宅急便控、電子楽器の修理サービスの実施報告書や、納品請求書や同居していた住居宛の郵便物から、両者が同居していた事実が確認できることや、
医療機関同意書の続柄に「知人」として記載されていたことに関しては、一見マイナス評価にも見られかねないと思われますが、「家族または保証人」欄にも請求人が署名押印していた事実について鑑みれば、知人と書かざるを得ない状況であった為、続柄に知人として記入しただけで、実態としては内縁関係であったと社会保険審査会において評価されたと考えられます。
以上のことから、請求人はAによって生計を維持した事実上婚姻関係と同様の事情にある者という結論になりました。
カテゴリ:
2025年4月 9日 11:11